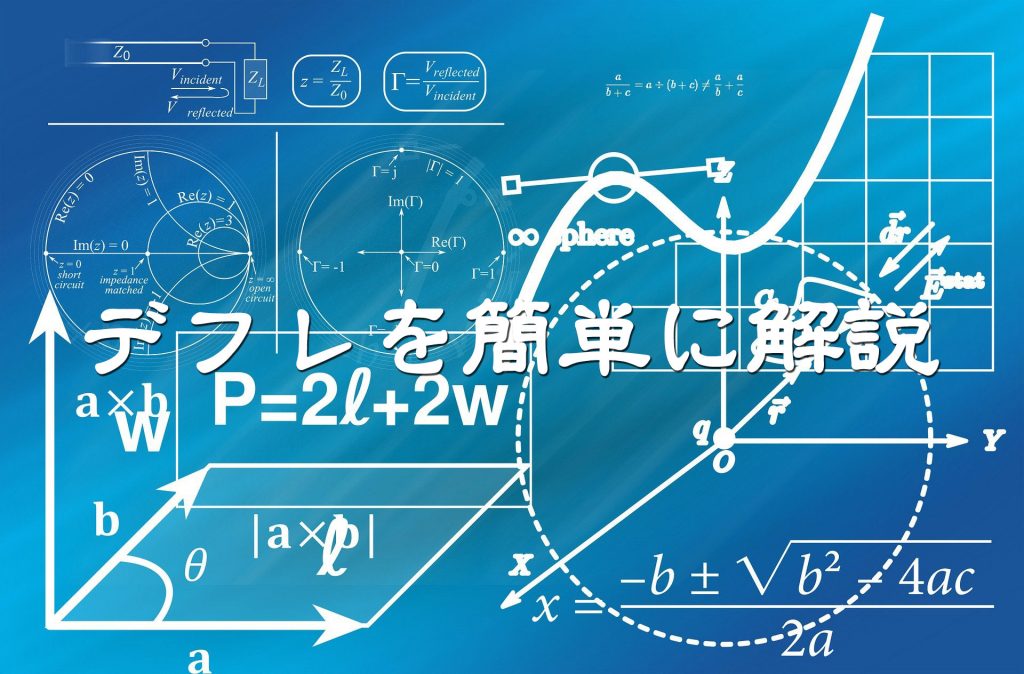
報道やニュースでデフレという言葉を聞きます。しかし、いまいちデフレについてわからない人も多いでしょう。何だか難しそうに聞こえる言葉ですが、デフレは難しいことではありません。
今回の記事ではデフレとは何かを簡単に解説します。簡単に解説しすぎると内容がスカスカになるので、深掘りしてデフレスパイラルやデフレの原因、脱却方法にまで言及しました。
この記事を読むだけで、デフレの全貌が簡単にわかります。
デフレとは
デフレとは「持続的に物価が下落していく経済現象」です。
デフレは正式にはデフレーションと呼びます。英語では「Deflation」と書きます。
デフレによる物価の下落とは貨幣価値の上昇と同義です。たとえば、昨日は100円でパンが1つ買えました。今日は100円でパンが2つ買えました。
この話を分解すると、パンは1つ100円から50円になっています。これが物価の下落です。
一方、100円の価値はパン1つ分から2つ分に増えました。これが貨幣価値の上昇です。
IMFや内閣府では「2年以上の継続的な物価の下落」をデフレと定義しています。
ハイパーインフレ以外では、インフレよりデフレの方が弊害が大きいです。
デフレ=物価下落、貨幣価値上昇と覚えると簡単ですよ。
デフレの反対の現象であるインフレについては、以下の記事で解説しています。インフレについても知りたいならおすすめです。
デフレの原因
需要の過少がデフレの原因です。数式にすると「需要<供給」がデフレの状態です。需要と供給のギャップのことを需給ギャップと呼び、需給ギャップが大きいほどデフレは深刻化します。
需要が少なくなる原因はいくつかあります。
たとえば、金融引き締めによって長期金利が上がると、資金需要が減少します。金利が上がったことで「借りようと思っていたけど、やっぱりやめた」となるわけです。
借りたお金は投資や消費に使われます。すなわち「お金を借りる=需要が増える」となります。
逆に「借りるのをやめる=需要が減る」こととなり、デフレの原因の1つになります。
他にも、政府支出の縮小はデフレの大きな原因です。政府支出とは政府が消費・投資することです。消費や投資とは需要です。政府支出が減ると需要が減り、デフレの原因になります。
つまり、政府による緊縮財政がデフレ圧力となります。
合成の誤謬とは
合成の誤謬はデフレの説明によく出てきます。
デフレの原因は需要が足りないことでした。需要を増やしたらデフレは解決します。では、民間はデフレのときに需要を増やせるでしょうか?
デフレでは需要が減るので売り上げが下がり、企業はコストカットに走ります。
企業がコストカットに走れば人件費も削られるため、個人の所得が減少して節約に走ります。
節約やコストカットは需要を減少させます。
このように、デフレの中で合理的な行動を企業や個人がとるほどデフレは深刻化します。ミクロ(個人・企業)では正しい行動が、マクロ(経済全体)では間違った結果を引き起こすことを「合成の誤謬」と呼びます。
デフレの経済への影響
デフレは経済に悪影響を及ぼします。
デフレになると企業は売り上げが下がります。需要が足りていないからです。売り上げの下がった企業はコストカット、リストラなどに走り失業率が上がります。
人件費も下げられますので、物価下落以上の速度で所得が下落します。
くわえて、研究費や開発費、設備投資なども削られます。研究費や開発費のカットでイノベーションが起きにくくなります。
こうして、名目経済成長率もマイナスになります。
非常に簡単にまとめれば、デフレは国全体を貧困化するのです。
デフレスパイラルとは
デフレに陥ると、次はデフレスパイラルが襲ってきます。スパイラルとは循環のことです。物価が下落し、それ以上の速度で所得が下落して需要が減少し、さらに物価が下落するというデフレスパイラル(循環)が起こります。
需要が過少なため、ものやサービスを売るには価格を下げるしかありません。価格を下げるためにはコストカットが必要です。人件費や設備投資などを削り、企業はリストラも行います。
国民の所得は人件費カット、リストラなどで減少します。個人は節約に走って生活費を削ります。
こうして企業、個人が合理的に行動すると需要がさらに減少します。需要がさらに減少するとコストカットに走り――と、無限に循環するのがデフレスパイラルです。
一旦デフレスパイラルに陥ると民間では抜け出せません。政府が財政出動をして、支出を増やすことで需要を増加させるしかありません。
デフレを脱却する方法
デフレを脱却する方法は簡単です。政府が支出を増やして需要を生み出せばいいのです。政府支出を増やす政策を財政出動や積極財政と呼びます。
デフレを脱却するためには積極財政がもっとも効果的です。
他にも、ゼロ金利でなければ金融緩和も効果があります。金融緩和で金利を引き下げることで借りやすくし、資金需要を満たすことで需要を増加させられます。
しかし、金融緩和はゼロ金利では効果がありません。それ以上、金利を下げられないからです。
日本経済は2016年、2020年もインフレ率がマイナスでした。デフレが「物価下落が2年以上継続すること」なら、インフレの定義は「物価上昇が2年以上継続すること」です。
日本はときどきインフレ率がマイナスになるので、インフレとは言いがたい状況です。
政府も認めるようにデフレ脱却道半ばでありデフレ気味です。
しっかりとデフレを脱却するためには積極財政しかありません。
まとめ
デフレという単語は一見すると難しそうですが、知ってしまえば簡単です。ただ、物価の下落や貨幣価値の上昇がやや理解しづらいでしょうか。このハードルさえ超えれば、デフレへの理解は一気に進みます。
日本は長年、デフレに苦しんできました。今もまだ、デフレから完全に脱却したとは言いがたい状況です。
デフレを放置すると多くの人が貧困化して不幸になります。デフレ脱却こそ、最優先に成し遂げられなければなりません。

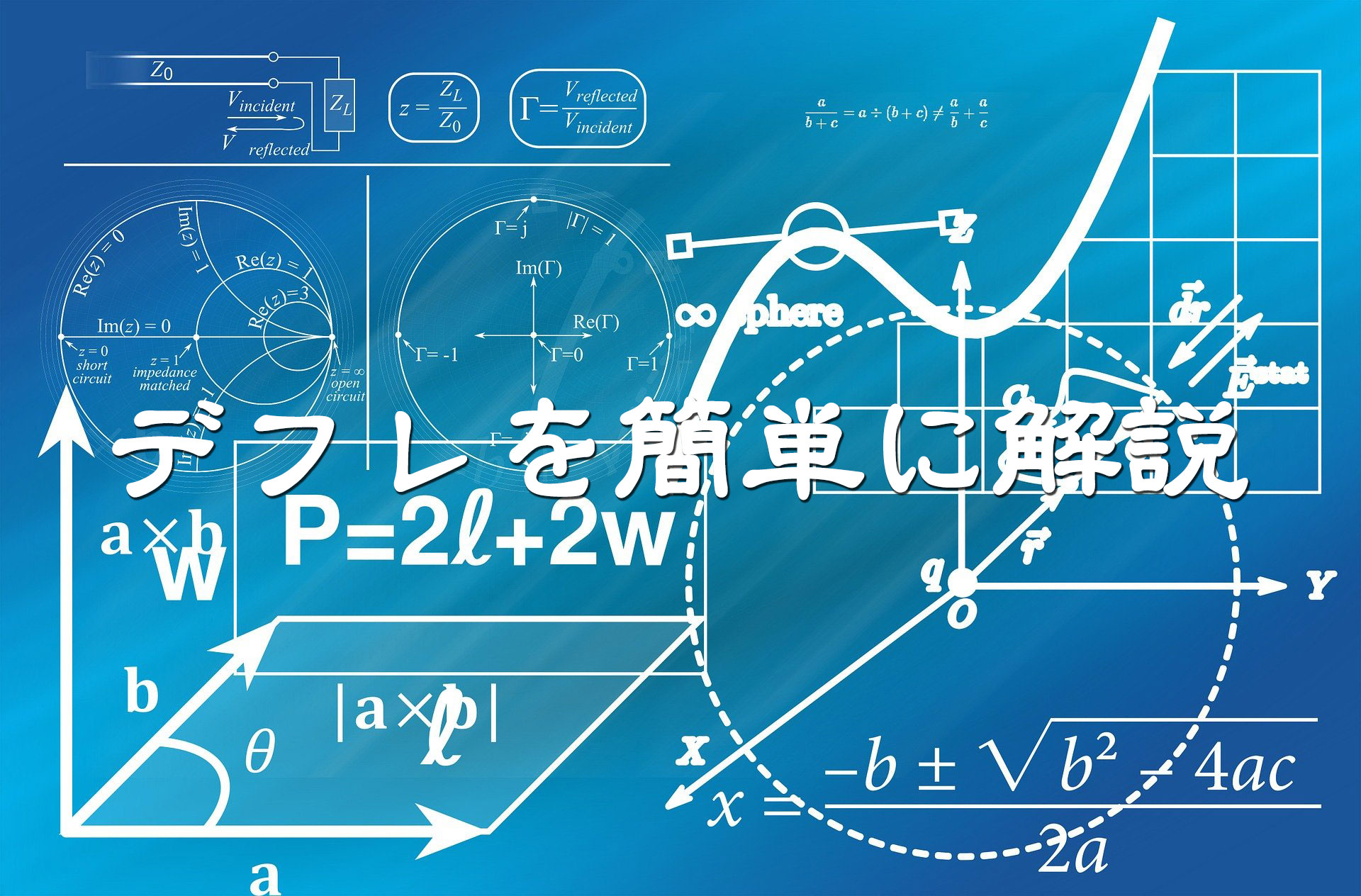



デフレスパイラルは実在しない。
リフレ派がバラマキを正当化するために捏造した嘘。
経済史を学べば、デフレ・インフレに関係なく各国が成長してきたことがわかる。